noteでは「あとがき」や、応援してくださる方へのページも用意しています。
よろしければ、のぞいてみてください。
東京地裁が旧統一教会の「継続性」を認定した理由
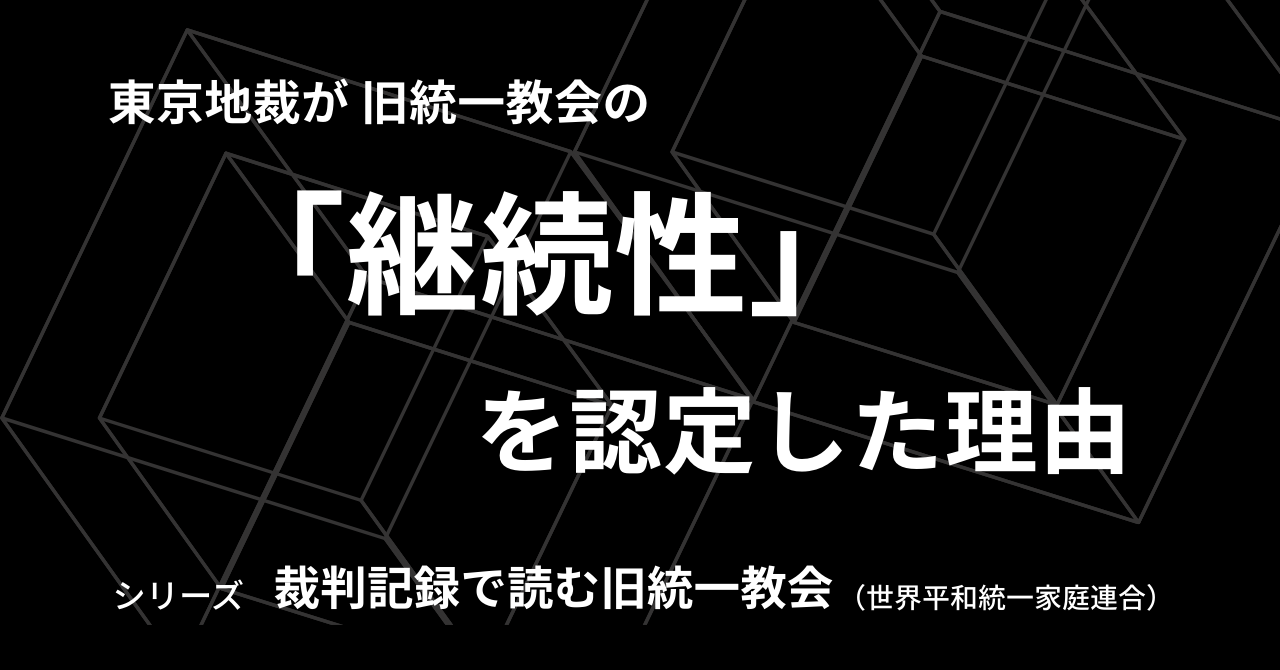
東京地裁による世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」「教団」と表記します)に対する解散命令決定文において、最も重要なポイントは「被害の継続性」を司法が認定したことにあるといえます。
そこで、決定文ではどのように継続性が認定されているのか、要約のうえ解説してみたいと思います。1
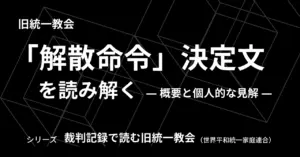
概要
教団は2009年に「コンプライアンス宣言」を出し「これからは改革していく」と自ら約束しました。にもかかわらず、実際には根本的な改善が行われた形跡は乏しく、被害は縮小したように見えても途切れることなく続いていた。これが東京地裁の出した結論でした。
特に決定的だったのが、文科省が行使した「報告徴収権(質問権)」への不誠実な回答態度です。
このやり取りの積み重ねこそ、地裁が「改善は実効性を欠き、被害は継続している」と判断する決め手となりました。
地裁が問題視した3つの点
まず、東京地裁は、教団の問題を「本件問題状況」2として大きく3つに整理しました。
- 弱い立場にある人への勧誘
入信前から家庭の不和や不幸な出来事、高齢などで判断に制約がある人たちがターゲットとなりやすかった。 - 「恨みを持つ霊の因縁」を解いて繰り返し献金を説得
教団の教えの中で「不幸は霊の因縁によるもの」等と説明され、その解消には献金等が必要と繰り返し伝えられた。対象者の問題と献金等が結び付けられる教育や指導、勧誘が継続的に行われた。 - 生活破綻に至る献金
借金や財産の処分で資金を捻出し、本人や家族の生活維持に重大な支障が出るほどの献金が繰り返される事態が生じた。
このような問題状況が、教団の責任を認めた32件の民事判決において認められ、それらには似たような傾向があり、かつ献金勧誘の行いそのものが教団の教理の実践とされていた背景事情もあることから、こうした問題ある献金勧誘の行いは「コンプライアンス宣言」が発出された2009年までの間に「全国的に、少なくない割合でみられた」と東京地裁は「推認」しています。3
こうした状況が「コンプライアンス宣言」以降、本当に改善されたのか――これこそが本決定の焦点となる部分です。
コンプライアンス宣言以降も消えない「被害」
教団は「2009年以降は改善した」と主張しています。確かに、表面上の数字を見るとコンプライアンス宣言後に不法行為が認められたのは2件3名のみと、顕在化する被害件数は減ったように見えます。
しかし、実際には裁判外の示談だけでも179名、約9.8億円(9割超が100万円以上)が処理されました。4さらに、コンプライアンス宣言後も長く献金の領収証を出して来なかったことや念書無効判決が6件存在する5などの状況を踏まえると、東京地裁は「数字が減った=改善」と単純に見ることは出来ないと判断しています。
考慮すべき被害の類型
これを検証するに先立ち、東京地裁は、本件における被害の現れ方を、大きく以下の3つに分類しました。6
- [a] 被害を訴える場合
訴訟提起や通知書の送付など、外部に問題を明確化するケース。 - [b] 教団・信者との間で非公式に解決する場合
当事者間で示談や弁済を行うが、公的記録に残らないケース。 - [c] 被害はあるが訴えない場合
労力や時間、心理的負担のために泣き寝入りするケース。
[a]の数が減っているからといって、本当に被害が減ったとは限りません。裁判外示談や一時的な対応によって、表面上は数字が減っているように見える場合もあるからです。また、[b]や[c]のケースも考慮する必要があります。
顕在化した被害だけでは全体は見えない
これを具体的に検証していきます。7
例えば、2010年以降に成立した裁判外の示談における被害金額の回収率が56%です。これは被害者の立場として、訴訟にかかる期間や労力を考えれば被害額の半額程度が戻って来るなら示談で解決する方法を選択した結果とも考えられます。
また、教団に送付された通知書のうち、被害の発生時期が明確でないものは、令和4年に18件、令和5年には124名分あり、この中にコンプライアンス宣言以降の被害も含まれている可能性があります。つまり、顕在化した被害[a]の数は、単純な179名にとどまらないと考えられるのです。
さらに、教団法務局の会議資料からは、被害者が通知書を送る前に事前解決された件数が実際に送られた件数を上回ることを示唆する内容も確認されることから、顕在化しない[b][c]の被害も相当数存在すると見込まれます。
さらに、179件の通知書の大部分は、従前から問題となっている問題ある献金勧誘行為について指摘するものでした。つまり、コンプライアンス宣言以降も、根本的な構造や方法論は変わっていなかった可能性が高いと判断されました。
「コンプライアンス宣言」の実効性を検証する
以上見てきたように、東京地裁は単なる表面化した数字上の改善だけを見て「継続性はないですね」という判断を行いませんでした。そこで、教団が信者の行動を指導・監督してきたのかどうかといった、教団としての取り組みやその実情面を検証し判断することにしました。8
教団に信者を指導監督する力はあったのか?
教団はしっかりした本部組織とその下の全国各地の地方組織をもち、信者の宗教活動に問題があれば指導監督することは十分可能な体制になっていたはずです。にもかかわらず実際に献金勧誘行為を行っていたとされる信者組織「信徒会」9に対して、教団が指導の通知を出した形跡がうかがえませんでした。
そもそも教団とは別の独立した組織として「信徒会」があったかどうかさえ東京地裁は強く疑問視していますが、それをおいても教団が信者の活動を指導できる力はあったはずである、と東京地裁は指摘しています。
教団に指導監督する機会はあったのか?
力だけでなく、機会も十分ありました。
たとえば、1984年の「青森事件」後、1987年に教団は東京都から「信者を指導するように」と行政指導を受け、いわゆる「霊感商法」による被害申告は一時的に減少していきました。ところがその後も、2007~2009年には信者が経営する会社による4件の刑事事件(「新世事件」等)が発生し、しかもその手口は過去の霊感商法から連続性があるものでした。さらに、コンプライアンス宣言が出される直前までの時期には、21件の民事判決で117名もの原告に損害賠償が認められています。これに訴訟外の和解や裁判外の示談を含めると、被害者は879名、総額は約100億円にものぼります。
これらの事実から見ても、教団は信者の活動が深刻な被害をもたらしてることを十分に認識し、かつ信者を指導する契機も機会も繰り返しあったにも関わらず、それをしなかったとさえいえるような状況である、と東京地裁は認めています。
改善のための具体的な施策が行われてきたのか?
これにより東京地裁は、旧統一教会をめぐる問題は「相当に根深い」と見ました。それだけに「本質的で実効性のある対策」がなければ問題の状況が解決したとは判断できない、つまり「継続性がある」と判断するのが合理的であると考えました。10
この考え方に基づいて具体的な検証を行ったところ、結果は次のようになりました。
- まず全国の信者に対する大規模で実質的な調査があってしかるべきだが、行われていない
- 「対策を行っている」という供述のみで、その裏付けとなる説明資料等の提出がない
- 教団は、文科大臣に求められたKPIに関する資料を十分に提出していない
- コンプライアンス違反があった場合の具体的方策が実際に行われた形跡がみられない
- コンプライアンス違反者への制裁等を行った形跡がみられない
ゆえに「コンプライアンス宣言後も根本的な対策がとられず、問題状況は残存している」、つまり「継続性はある」という判断を、東京地裁は下すに至ったのです。
決定的だった「質問権」への不誠実回答
ここで特に、上記の③と④、報告徴収権(以下「質問権」)への教団の対応について、もう少し詳しく記述したいと思います。質問権の実施状況については報道等で詳しく報じられることはありませんでしたが、地裁決定文にはその内幕がかなり詳しい状況まで記されており、大変興味深いものです。
文部科学大臣は、コンプライアンス宣言以降の改善の実態を把握するため、質問権を行使して旧統一教会に対し報告を求めました。その中でポイントとなるのは「KPI(改善指標)の運用実態(上記③)」と「コンプライアンス違反があった場合の具体的な方策(上記④)」です。
KPIの詳細報告を拒否
文科大臣は、教団が信者の法令遵守の状況を客観的に評価するために導入するとしたKPI(重要業績評価指標)について、以下について具体的に説明するよう教団に求めました。
- どんな目標を立てたのか
- その指標を選んだ理由は何か
- 実際に現場でどう当てはめ、どう評価しているのか
- 法務局など関係部署にどう展開しているのか
- KPIが実際に機能している証拠
その目的は、教団が設定した目標の達成にこのKPIが役立つものかどうかを検討するためでしたが、これに対する教団からの実質的な回答はなく、回答しない理由の合理的な説明もありませんでした。
コンプライアンス違反への対応状況も回答拒否
また教団は、コンプライアンス違反が起きた場合の具体的な方策(調査・改善指導・改善されない場合の処分等)を定めていました。文科大臣は、これらの実施状況も報告するよう繰り返し求めました。
ところが教団は「特定の事案に対する資料が出ていないからといって実績がないということはない」などと回答するにとどまったため、教団が自らやると定めた方策を実施したのかどうか、その形跡を確認することができませんでした。
自ら掲げた「改善」を示さなかった教団
以前の記事にも書きましたが、なにも文科省は教団に対し無理難題をふっかけた訳ではありません。2009年の「コンプライアンス宣言」を通じ、教団自ら「やる」と決めたことの具体的な実施状況を報告してくださいとお願いしたまでのことです。2022年12月時点で教団本部職員は110名、11これだけの規模の組織体であれば、そう無理なく準備できる類の資料といえるのではないでしょうか。
万一、それでも提出することが難しければ、その理由をきちんと先方に説明し、相談のうえ双方納得できる形のものを提出する等、やりようはいくらでもあったはず。
ところが、教団は上記のような信じられないほど高慢な態度で所轄官庁に対応し、更に不回答による過料10万円の処分にも「質問権の行使自体が違法だ」という理由で抵抗した挙句、最高裁まで争って敗訴しています。12
このような態度を取るのですから、相手方に「やると言ったこと、やってなかったんだろうな」と推認されても文句は言えないでしょう。そのうえで「今はやってない」「我々は改善している」といくら強弁したところで、納得感はまるでありません。
私は個人的に、この質問権への対応こそが教団にとって致命傷になったのではないかと考えています。
まとめ
ここまで、「コンプライアンス宣言」以降の旧統一教会による被害状況を検証した過程について、私なりにまとめてみました。
地裁決定文について、報道等では教団の資産額や残余財産の帰属先(天地正教)が注目されましたが、最も重要なのはこの「継続性」を認めた箇所といえるでしょう。
また、地裁決定文が「質問権の行使」と教団側の回答拒否について、その詳細を明らかにしたことは注目に値します。宗務行政や宗教学の研究において、貴重な資料として歴史に残るものでしょう。
さて、教団側はこの地裁決定を高裁でどう覆す計画でしょう?教団が発出した抗告理由書(要旨)13も拝読しましたが、決定打に欠けるとしか私には思えません。教団側の抗告についても、機会があればまとめてみたいと考えています。
- この記事で紹介する内容は東京地裁決定文の 第3 当裁判所の判断→2 法81条1項1号所定の解散命令事由に基づく解散の可否について→(2)「法令に違反」する行為の有無・内容及び規模 に基づきます。以降の注釈で原文の位置を示す箇条書きの記号・番号についてはすべて上記(2)以降についてのものになります(脚注11.を除く)。 ↩︎
- ア-(イ)-c- (c)「 32件の民事判決における類型的傾向が利害関係参加人の信者による献金勧誘行為に存在していたと認められること」-〔2〕
「教団の信者による献金勧誘行為については、少なくとも上記の期間において、全国的に、【1】教団の信者が、入信前から自身や親族に、複雑な家庭環境、不幸な出来事、高齢等による判断基準の制約等があるなどの困難な事情を抱える者(一般に、次の【2】のような教育・指導及び勧誘による影響を受けやすい者)に対し、【2】教団の教理を伝導する過程で、その教理に関連して、種々の深刻な問題の原因の多くは怨恨を持つ霊の因縁等によるものであり、このような問題を解消するためには献金等が必要である旨を繰り返し申し向けるなどして献金等を行うよう勧誘し(種々の深刻な問題と因縁等とを結び付けた、教育・指導及び献金等の勧誘の反復継続)、【3】その結果、借財等により原資を捻出するなどして、本人や近親者等の生活の維持に重大な支障が生ずる献金等を繰り返し行わせる(生活の維持に重大な支障が生ずる支出という結果の反復連続)ものとなるおそれがある状況が生じていたと認められる(以下、そのようなおそれのある状況を指して「本件問題状況」という。)。」 ↩︎ - 同上
「そうすると、32件の民事判決において、不法行為の成立が認められた献金勧誘行為についてみられた(中略)類型的傾向が、少なくとも、昭和50年代後半から、コンプライアンス宣言の出された平成21年頃までの間、利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について、全国的に、少なくない割合でみられたと推認することができる。」 ↩︎ - イ-(エ)-a裁判外の示談を中心に相当程度の被害が存在すること ↩︎
- イ-(ウ)-c-(b)対策の具体的内容及び実情につき法令遵守実現の観点から問題のある部分がみられること ↩︎
- イ-(ウ)-a 被害申告(訴訟提起等)の傾向に係る考慮要素 ↩︎
- イ-(ウ)-a-(a)数値面に係る考慮要素, (b)内容面に係る考慮要素(コンプライアンス宣言後の被害申告の内容) ↩︎
- イ-(ウ)-b 被害申告の傾向に係る考慮要素を踏まえたコンプライアンス宣言後の本件問題状況の有無及び程度についての検討方法等 ↩︎
- 筆者の入手した判例で「P6会」と表記されているものを、本記事では「信徒会」としています。「利害関係参加人(教団)から独立した別個の組織である連絡協議会又はその後継組織であるP6会」とされていることから「信徒会」を指すものと判断しています。 ↩︎
- イ-(ウ)-b-(c)コンプライアンス宣言後の本件問題状況の有無及び程度についての検討方法
「そうすると、本件問題状況は相当に根深いものであって、コンプライアンス宣言及びその後の同様の施策にあるように、禁止行為を定めるなどして教会指導者等に伝達や周知するといった対応等があったとしても、本件問題状況に対する対策として、利害関係参加人の組織体質及び相当数の信者の行動の在り方を大きく変化させるような根本的な対策(本質的で実効性のある対策)が講じられたといえなければ、本件問題状況は残存していくと考えるのが合理的である。 ↩︎ - 認定事実1-(1)-(ア)-c 本部の職員数 ↩︎
- 最高裁判所 旧統一教会に過料10万円を命じる | NHK | 旧統一教会 ↩︎
- 解散命令事件の抗告理由書を東京高裁に提出しました|ニュース|世界平和統一家庭連合 ↩︎
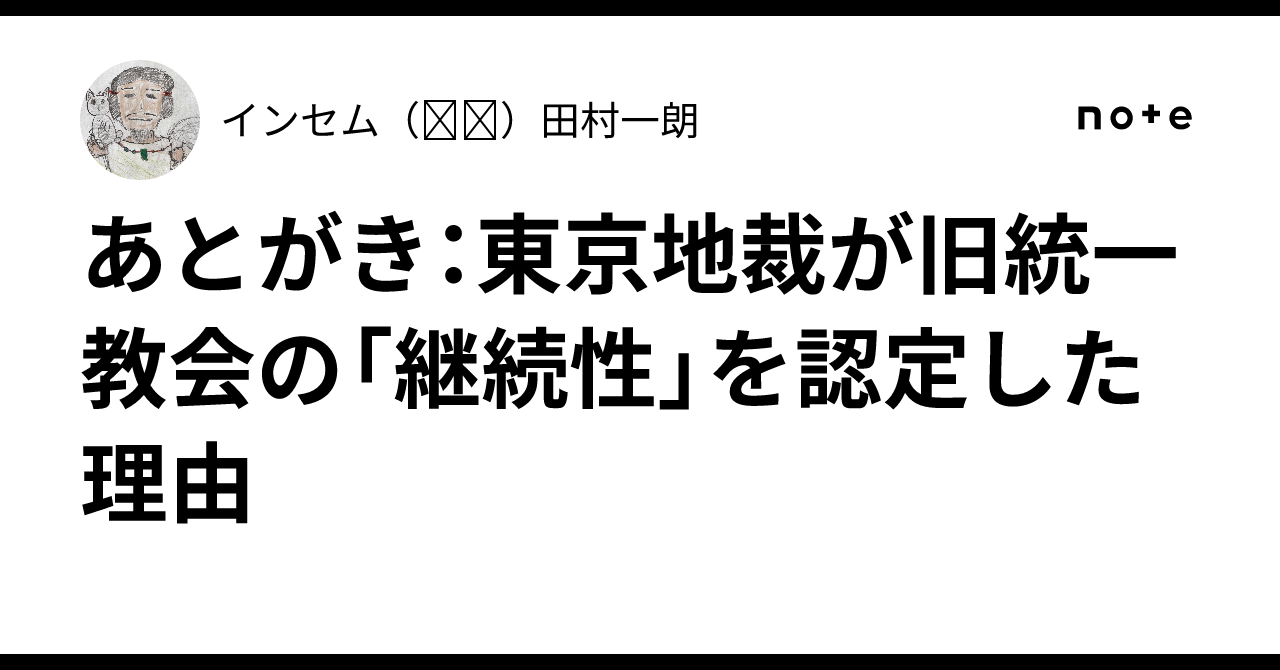




コメント