noteでは「あとがき」や、応援してくださる方へのページも用意しています。
よろしければ、のぞいてみてください。
旧統一教会「解散命令」決定文を読み解く――概要と個人的な見解
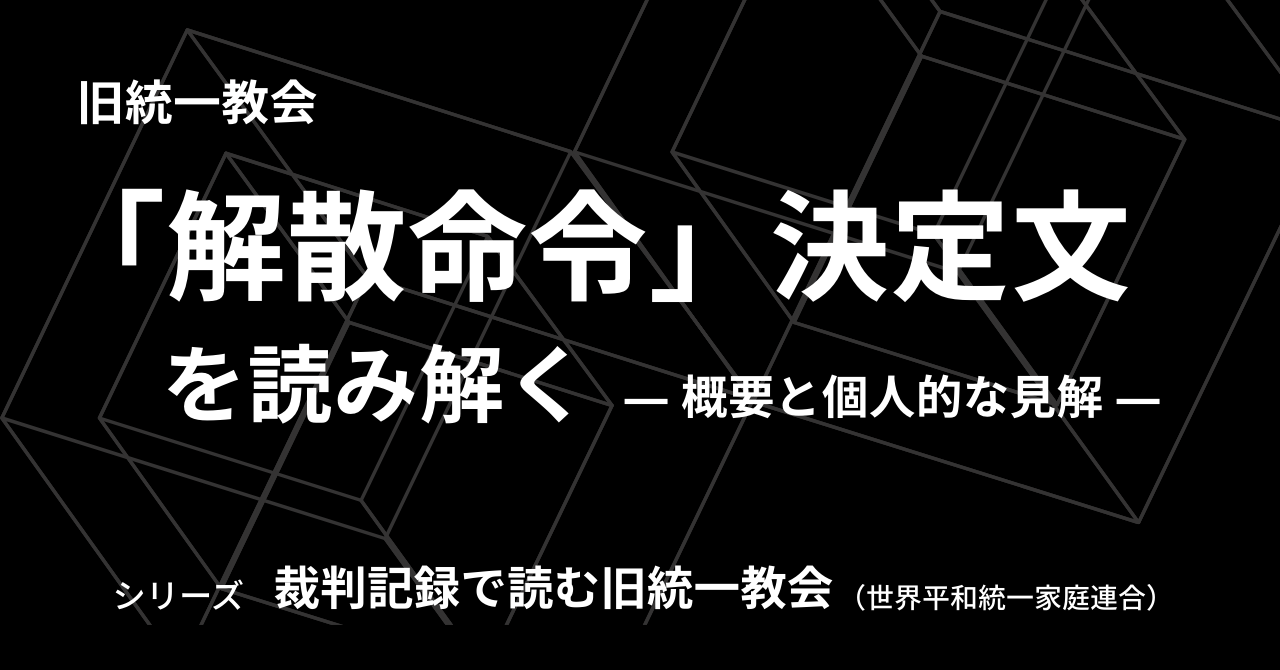
令和7年3月25日に東京地裁が出した「世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」「教団」と表記します)に対する解散命令の決定文1を全文読みました。
当日の新聞等で要旨2が報じられているものの、やはり全文を読まなければ理解・納得ができないと思い、判例3を入手し読み込んでみました。
この記事では、決定文全文の概略と、それを読んだ当事者である私個人の見解について綴ります。
決定文の全体像
まずは大まかな構成です。4
- 主文
教団を解散する - 前提事実
設立から解散命令に至るまでの経緯や、多数の損害賠償請求の存在 - 双方の主張
文科省(申立人)と教団(利害関係参加人)のそれぞれの意見 - 裁判所の判断
事実認定、解散要件への該当性の検討
なぜ「決定」なのか?
なぜ「判決文」ではなく「決定文」になるかというのは分かりにくいところだと思います。それは、この裁判が行政処分(法人格の取り消し)が妥当かを争う行政事件になるからです。ですので結論は「判決」ではなく「決定」と表現されます。
どのように論じられているか
前提事実5
まず、教団に関わる重要な事実を整理しています。
- 元信者らによる多数の損害賠償訴訟とその認容
- 信者による霊感商法や刑事事件
- 「コンプライアンス宣言」以降の改革の状況
- 安倍元首相銃撃事件後の質問権行使や社会的反応
双方の主張の要旨
次に、裁判所によって文科省(「申立人」)と教団(「利害関係参加人」)の主張が、項目ごとに整理対比され、まとめられています。後ほど、この部分の概要を一覧表で掲載します。
東京地裁の判断
最後に、東京地裁による検討と判断が示されています。
認定事実
先の「前提事実」+提出された証拠+裁判での審問を通じ、東京地裁が「事実であること」を認定した項目が書かれています。大きく、以下について認定されています。
- 宗教法人の概要
- 霊感商法・不法行為関連
- 教団信者による刑事事件
- 「コンプライアンス宣言」とその後の施策
- 教団の名称変更等(平成27年)
- 社会的事件・その後の情勢
- 報告徴収手続・質問権行使
- 損害賠償請求の内容・規模
検討の基準となる条文
宗教法人解散が妥当か否かを検討する根拠になる条文は、宗教法人法第81条1項1号です。
宗教法人法 第81条
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
検討の順序
それに基づき、大きく以下のような順序で検討が進みます。
- 条文の各文言の解釈「宗教法人について」「法令に違反して」「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」
- 教団の行為が「法令に違反」といえるか。その内容および規模。
- 教団の行為が「宗教法人について」にあたるか否か。
- 教団の行為が「公共の福祉を著しく害した」といえるか否か。
- 信教の自由との関わりを考慮し、解散命令が必要でやむを得ないかを判断
特に②「法令に違反」する行為の有無・内容・規模等については、教団による「コンプライアンス宣言」の前と後に分けて非常に詳細に検討されており、この決定文で最大の分量を占めています。
三者の主張の要点一覧表
以上について、文科省・教団・東京地裁の見解のポイントを一覧表にまとめました。
| 項目 | 文科省 | 教団 | 東京地裁 |
|---|---|---|---|
| 1.「宗教法人について」の解釈 | – 法人の行為は代表者に限定されず、広く判断すべき。 | – 法人の行為は代表役員等に限定されるべき。 | – 法人の行為は広く判断されるべき。 -オウム事件判例は個別事案であり、行為主体を限定する会社法とは異なる。 |
| 2.「法令に違反」の解釈 | – 法令には民事の不法行為も含む。 – 公共の福祉に反する行為は許容されない。 | – 法令違反は刑事法令に限るべき。 – 民法709条違反は解散要件に含まれない。 | – 民法709条違反も含まれる。 – 解散命令は信教の自由を不当に制約せず、相当性を逸脱した行為は違法。 |
| 3.「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」の解釈 | – 過去の重大行為で足り、改善は考慮不要。 | – 組織性・悪質性・継続性・緊急性・必要性がなければ解散不可。 | – 信教の自由と解散命令の趣旨を考慮。 – 過去・現在・将来の状況を踏まえ、解散が必要でやむを得ないかを判断。 |
| 4.「法令に違反」する行為の有無・内容・規模等 | ①未証し勧誘 ②因縁トーク ③他を犠牲にした献金 – 被害多数・巨額・深刻な苦痛 | – 献金は信仰心に基づく自発的行為。 -証言は信用できず、和解は自由意思。 | – 長期・全国的に多数・巨額の不法行為が存在し、看過できない被害が継続。 |
| 5.「宗教法人」の該当性 | – 献金勧誘は教団の活動そのもので該当する | – 献金は信者の自発行為で該当しない | – 社会通念上、献金勧誘は教団の行為で該当する |
| 6.「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」の該当性 | – 長年多数の被害、改善なし → 該当する | – 不法行為は存在せず、過去の問題だけでは解散不当 | – 悪質性・重大性・継続性あり → 該当する |
| 7.結論 | 解散命令は妥当 | 解散命令は不当 | 解散命令は必要かつやむを得ない |
決定文において特徴的な点
決定文の全文を読み、私自身の見解や感想を3点ほど挙げてみたいと思います
「推認」は十分に合理的
「『推認』で解散させられるのは不当である」等の主張がみられましたが、決定文を見ると「合理的に推認できる」といった風に「合理的」という文言がついている箇所が複数ありました。
たしかに「完璧な証拠がそろわなければ宗教法人は解散命令の要件に値しない」ということでは、宗教法人は徹底的な証拠隠滅をすれば悪事の限りを尽くせてしまいます。それは宗教法人法に定められた解散命令の趣旨に沿いません。
東京地裁は、直接的な証拠や証言ばかりでなく、それらを多角的に考慮し、複数の事実をもとに幾重にも検証を重ね「合理的」といえるまでの推論に高めていると私は思いました。
質問権に対する教団の対応が致命傷となった
その合理的な推論は主に、教団が発出した「コンプライアンス宣言」(2009年)の後の実態を検討する際に用いられています。単純に宣言後に訴訟件数など目に見える数字が減っていることだけでなく、類例のない規模で深刻な問題を引き起こしてきた事実に鑑み、この教団の体質が本当に改まっているか、改まった程度がどれくらいか等を東京地裁は見ようとしました。
ここで、文科省の質問権行使に対する教団の態度が、致命的な結果をもたらしてしまったと私は思いました。
認定事実によれば、文科大臣は教団自らが定めた改革の計画について、その指標や運用の仕組み、具体的な運用状況が分かる書類を提出するよう求めたそうです。6それに対し教団は、既に提出済みの一部関連資料を指し「これで十分と考える」や「(改革については)常時徹底している。特定の事案に対する具体的な資料を出さないから改善の実績がないということはない」等と言い、ひたすら提出を拒み続けてしまいました。7
この規模の法人なら通常存在するであろう書類。しかも教団自身がやると決めた取り組みについての資料が求められたにすぎず、文科省が是が非でも教団を解散に追い込むために無理難題をふっかけたものとはいえません。
東京地裁も、これでは教団の改革状況を十分に検討できないばかりか、所轄官庁に対するこのような頑なな対応に疑問を持ってもおかしくありません。加えて、その他多数の要件も考慮すれば、宣言後も「なお看過できない程度の規模の被害が生じている」との判断は至極真っ当であると私は考えざるを得ません。
「信教の自由」への配慮
そして東京地裁は「信教の自由」の観点を十分に配慮しているといえます。
まず、上記3の「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」の解釈について、双方の主張を特に「信教の自由」の観点も加えて検討すべきとして、項目を分けて論じています。
更に結論について、単に「解散命令は妥当」ではなく「必要かつやむを得ない」となっています。
この教団が宗教法人法に定められた解散命令の要件に合致することを論を尽くして検証し、解散命令制度の趣旨に鑑み、かつ「信教の自由」の観点や解散に伴う教団側の不利益についても十分に考慮し尽くしたうえでも、なお「解散命令は必要かつやむを得ない」という結論に至ったものです。
おわりに
この記事では、東京地裁による旧統一教会に対する解散命令決定文について、その概要を示しました。私自身の理解のために整理した内容を記事化したものですが、どなたかのご参考になれば嬉しい限りです。
なお、先に申し上げた通り正確性や中立性に欠ける部分があることも十分考えられます。この決定文は有料の判例検索のデータベースを使用し誰でも入手できますので、8可能であればぜひご自身で全文を読んでみられることをお勧めしたいと思います。
- 東京地方裁判所(第一審)/ 裁判年月日: 令和7年3月25日/事件番号: 令和5年(チ)第42号/事件名: 宗教法人解散命令申立事件 ↩︎
- 【決定要旨】旧統一教会の解散を決定 東京地裁の判断理由は [旧統一教会問題]:朝日新聞 など ↩︎
- 本記事では決定文の原文ではなく、判例検索データベース(有料)で提供される判例に基づいて述べています。判例検索データベースは大きめの公共図書館で無料で提供されている場合もあります(通常、印刷代は別途所要)。 ↩︎
- 本記事における構成順序や付番等は決定文原文に沿ったものではありません。 ↩︎
- 原文によると「掲記の証拠(略)及び審問の全趣旨により容易に認められる事実」とのことです。 ↩︎
- 認定事実(8)本件報告徴収手続等 ア (ア)より:
文部科学大臣は、本件報告徴収において、利害関係参加人の設定したKPIが自らの設定した目標達成のために有用であるかどうかなどを検討するためには、〔1〕利害関係参加人の設定した目標等、〔2〕利害関係参加人が目標達成のために決定的に重要なものとして選出した指標、〔3〕実際に利害関係参加人で起きる事象と当該指標への当てはめや評価方法、〔4〕利害関係参加人の目標と方針が利害関係参加人の一部門である法務局に展開された経緯や状況、〔5〕KPIの具体的な運用状況、について把握することを要するとの理解の下で、上記〔1〕から〔5〕までの諸点等について具体的に回答し、これらに係る資料を提出するよう繰り返し求めた(第2回、第5回~第7回報告徴収)。 ↩︎ - 認定事実(8)本件報告徴収手続等 イ(イ)より:
これに対し、利害関係参加人は、「2009年のコンプライアンスに関する公文を発出して以来、常時、コンプライアンスの徹底を指導しているが、その記録は報告徴収〔1〕で報告した資料が全てである。」、「常時、責任者や牧会者等の会議や現場のスタッフらの集会、面談等でコンプライアンスの徹底を指導し注意してきたのは、これまでの資料で示したとおりである。特定の事案に対する改善指導、制裁措置の資料を提出していないから、“実績”がないということはない。」などと回答しているところ、利害関係参加人が第1回報告徴収における回答の際に準備した資料を含め、本件報告徴収に対する回答の中には指導改善措置が行われたことを示す具体的な資料はなかった。 ↩︎ - 注釈1.および3.をご参照ください。 ↩︎
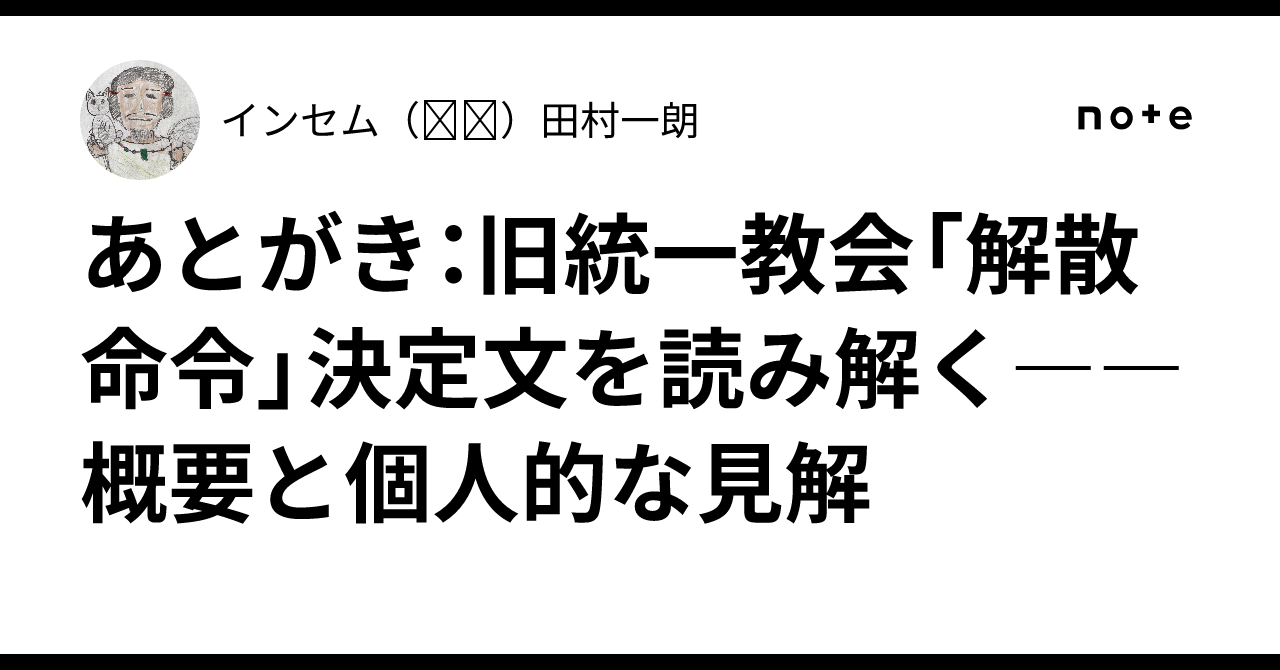




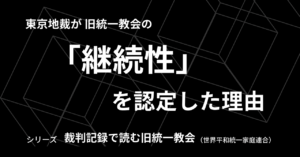
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 旧統一教会「解散命令」決定文を読み解く――概要と個人的な見解 […]